 昨日は夢を見ましたか?
昨日は夢を見ましたか?
願う夢と寝ている時に見る夢。
どちらも自分の脳が作り出している。 “夢があるとき” の続きを読む
寒さが増してきて、肩や首に力が入ってしましがちです。
リラックスできない状態も、同じく首や肩に力が入ります。
運動とは、『運を動かす』。
外に出て、歩くのもハイキングや紅葉の綺麗な景色を見ながらいいですね。


秋めいた空気の爽やかな朝になりました。無事に開腹手術を終えて5日目です。表面の傷は完全に閉じたようで、動いた際に中に痛みがあるというくらいになりました。
そして、ヨガの「考えると感じるは同時にできない」という教えも大変役にたちました。
燃えよドラゴン」という映画で
「Don’t think. Feel」
「考えるな、感じろ」というセリフが少林寺拳法をするシーンでありました。
この話は、ヨガのクラス中に頭の中に色んなことがでて集中できないという生徒さんへお伝えしました。

最近は、ハンドスタンドとヘッドスタンド(逆立ちのポース)が確実に安定してできるようになりたくて、日々もがいております。
壁なしで逆さまに立つこと。
コアとバランスで立つ。
先日バレエクリニックにて、新たに学んだこと。
人は立つ時に、膝を伸ばすと踵が押せて踏めている。土台が安定すると、骨盤と肋骨の向きもはまる。
“正しく立つ。ミラーニューロン” の続きを読む
 ”やさしい”とは。
”やさしい”とは。”やさしいヨガ”というタイトルをつけてみて、考えてみた。
辞書によると、優しいとは穏やかで好感がもてる。
思いやりがある。上品で美しい。つつしまやかである。
易しいとは、平易である。容易である。わかりやすい。
最近私が感じたやさしさ。
あなたが、嫌いと思うことはどんなことですか?
どんなことで、怒ったことがありますか?

夏も真っ盛りで、お祭りや花火など夏らしい行事を見かけることが多くなりました。
先日も近所で盆踊りが開催されていて、浴衣で着飾った人や楽しそうに踊る人たちを見て、とても幸せで平和な気持ちになりました。
しかし、その会場には人が沢山通行する道に座り込んで喫煙所の外でタバコを吸う人。
翌朝には吸殻やお酒の空き缶ゴミが、町中に捨てられていてとても嫌で怒りの感情が出てきました。
その嫌で怒りの感情を冷静に考えてみました。

吐くから吸う息がくる。
吐く息とともに大地に降りてくる。
先日、ヨガクラスでのグランディングの為のアシスト。
このインストラクションを聴いた時、私の中でのイメージは、広い草原に青い空。
雲は沢山あっていい。
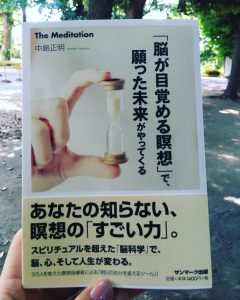
私のヨガティーチャートレーニングの先生である、中島正明氏が書籍”『脳が目覚める瞑想』で、願った未来がやってくる”を出版されました。
師と初めてお会いしたのは、昨年末ティーチャートレーニングの説明会でした。
ヨガのトレーニングなのに、潜在意識とか顕在意識とか囚われ、概念など。
予期せぬ師の言葉に驚くばかり。この人からは絶対に私の知らない色んなことを教えてもらいたいと迷うことなく受講を決断しました。
ヨガとは心の作用を死滅させること。
心の作用の完全停止によりサマディ、三昧がやってくる。
解脱した人。生きながらにして解き放てれている。
師はよく可能性しかないという。

精神的な感情が身体に影響を及ぼすのを感じる時。
緊張して、心臓の鼓動が強く早くなり、汗をかく。
恐怖に怯えて、心臓の鼓動が強く早くなり、肩に力が入る。
安心すると、心臓の鼓動が弱まり遅くなり、肩の力が抜ける。
こころの働きが、身体に影響を及ぼす。
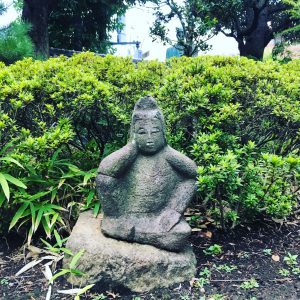
人は、過去を見ると後悔し、未来を見ると不安になる。
だから、今を生きる。
明日何しようかなと考えず、今自分が行っていることに集中して。
無意識に過去や未来に、囚われていることって結構あるんですね。
例えば、面接や大切な発表の場、コンテストや大会。
緊張したりするのは、失敗したらどうしよう。まだ起きてもいない失敗。
未来のことに囚われている現実。未来を見ると不安になる。不安からの緊張。
成功させて賞をとって、恩師に恩返しするんだ。
賞を取ること恩返しすること、思考が未来にいってますね。
初めて瞑想をしてみました。

今日は春めいたお天気で、なんだか桜がもう少しで咲くと思うとお花見の予定をたてたくなったりワクワクするいい日差しです。
そして、卒業式シーズンですね。
卒業式に行かれたお母様のお話を聞いただけで感動が伝わってくる。
先週3回目のお写経会に、祐天寺へ行って参りました。
「色即是空・空即是色』 【色即是空】〔仏〕〔般若心経〕 この世にあるすべてのもの(色)は、因と縁によって存在しているだけで 固有の本質をもっていない(空)という仏教の基本的な教義。 【空即是色】〔般若心経〕 宇宙の万物の真の姿は空であって、実体ではない。 しかし、空とは一方的にすべてを否定する虚無ではなく 知覚しているこの世の現象の姿こそが空である。
私には物質社会の概念や常識がこびりついて、理解しがたいですがそこを破り理解していきたいな。
☆実践
お坊さんのお話は、小学校での給食にでる牛乳瓶のキャップを誰が開けるのか。とある小学6年生のクラスで先生がすべての生徒のキャップを開けるのだそうです。それは、みんなが自分で開けられないから。40人くらい?毎日先生一人で開けるの?驚きました。